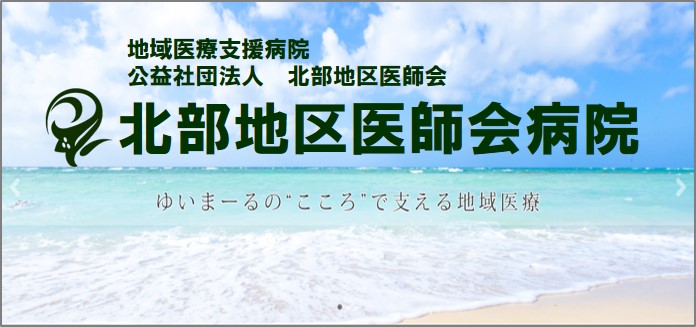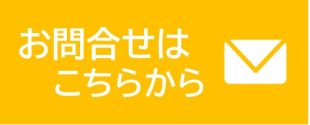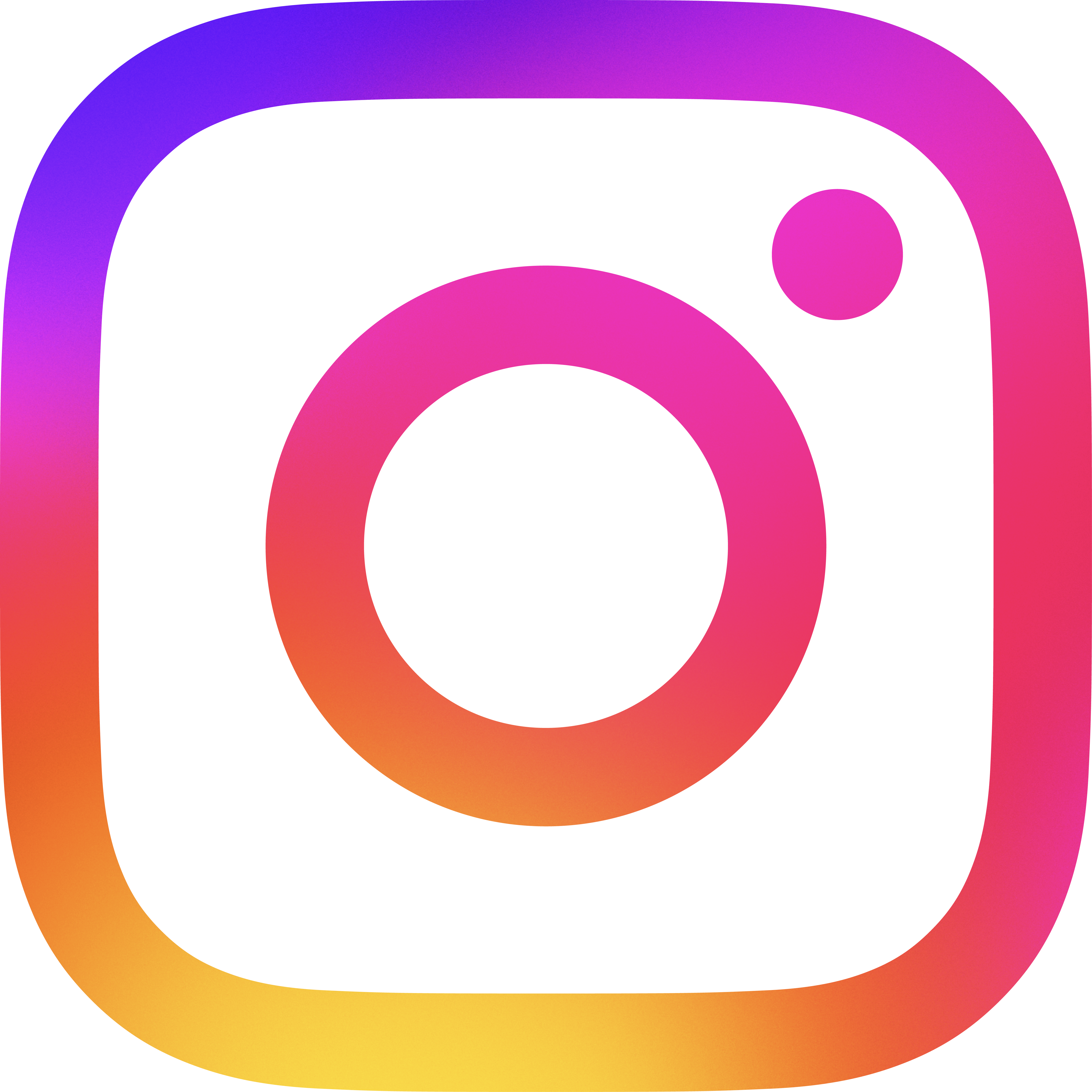RyuMic-北部地区医師会病院 初期臨床研修プログラム(令和7年度版)
目的
救急医療と保健予防活動・プライマリ・ケアを基本とし、総合的臨床能力を有する医師の育成を目的とする、総合診療方式基本研修とし、外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科を選択科として研修する。また2年間を通じて救急総合診療部門も平行し、初期救急医療からプライマリーケアを主とした研修ベースに問診・初期治療の実施から適切な判断能力を身につけられるようにする。
特徴
琉球大学病院(三次医療機関)と地域の中核を担う急性期病院(二次医療機関)及び地域に密着したプライマリ・ケアを実践する診療所等との連携
すべての研修医が一次医療機関から三次医療機関での研修が可能(ローテーションする診療科や時期はプログラム責任者との事前調整が必要)
県外を含む多くの研修協力病院及び研修協力施設による多様な研修
On the job training(OJT)の実践
研修医の性格や特徴、希望を加味して、適切なや指導医の選定を調整
診療科にとらわれない教育の場の提供(定期的な各科カンファレンス・症例検討会・レクチャー等)
研修プログラム責任者自らがチューターとなり、手厚く支援
ローテーションについて
1)オリエンテーション
研修開始後は、研修を円滑にできる医師として仕事を始めるためのオリエンテーションとインフォームドコンセント、チーム医療、保健医療、院内感染対策、医療事故防止など、医療を行うために必要な基本事項を学ぶ
2)共通研修(グランド・カンファレンス:全期間を通じて)
ローテーション研修では、研修が困難な内容を学ぶ目的で、(毎月2回)研修医全員が合同カンファレンスやスモールグループワークに参加する。研修医を受け入れている各診療科は、研修医が共通研修に参加できるように配置する。
3)ローテーション研修では、2年間で56週を基本必修科研修<内科24週、救急12週(内:救急8週、麻酔4週)、外科4週、2年目で行う小児科・産婦人科・精神科・地域医療研修4週(内:診療所4週、在宅医療4週)>、選択必修残り48週を自由選択科研修に充てる。
4)内科24週・救急12週については1年目で行う。
5)研修は、基本的に研修医が希望のコースを選択し、本院及び基幹型臨床研修病院・研修協力病院・施設で行われる。
6)共通研修には研修医全員参加する。
7)選択必修科は、選択科と合わせて期間以上の研修をすることが可能である。
8)2年間の研修期間のうち1年間以上は本院で研修を行う。
9)ローテーションについては、特に診療科より指定がない限り順不同であるが、1年目で内科以外の診療科を研修出来る期間は最高12週とする。4週から12週の間で行う研修を基本研修とする。研修医はこれらのうち1年間以上本院において研修し、残りを琉球大学病院や他の協力病院及び協力施設で研修する。ローテートの順番は卒後臨床研修委員会が調整する。
必修科研修と選択科研修
各診療科での研修
各科研修内容
当院では入職後、1年次研修医全員が「内科」ローテーションからスタートします。基本的な診察能力、カルテ記載法、各種検査の出し方およびその検査結果の理解の仕方等を身につけてもらい、その後、救急科、外科などの必修科、選択科のローテーションに移ります。この間、各科に1年次研修医は一人づつとし、重ならないようにしています。
胃・大腸・肝胆膵疾患を中心に診察しています。疾患の特性上、消化管内視鏡検査の重要性は大きく、胃カメラ・大腸カメラはもちろんのこと、ERCPや超音波内視鏡検査も毎週行っています。研修医には内視鏡検査や腹腔穿刺など手技にも積極的に関わってもらいます。
◆呼吸器・感染症科◆
肺炎・気管支喘息、COPDといった頻度の高い疾患から、肺癌、間質性肺炎、結核といった専門性の高い疾患まで幅広く対応してもらいます。研修医には、グラム染色や胸腔穿刺ドレーン留置、気管支鏡検査を積極的に行ってもらいます。
◆循環器内科◆
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)に対するカテーテル検査・治療を中心に、デバイスの植え込み(ペースメーカー/ICD/CRT-D)や不整脈治療(薬物治療・アブレーション)、末梢動脈疾患のカテーテル治療を行っています。
救急車搬送の患者さんと救急処置が必要な患者さんの初療対応と上級医と共に行ってもらいます。採血や末梢ライン確保、気管挿管、中心静脈カテーテル留置、簡易エコーなどの手技を習得するとともに、「問診・診察→鑑別疾患→検査オーダー→病態把握→上級医と治療方針についてディスカッション」という多くの診療の流れの中で経験を積んでもらいます。
◆麻酔科◆
一般外科・整形外科の手術における、全身麻酔、脊髄くも膜下麻酔、症例によっては硬膜外麻酔の穿刺、気管挿管、動脈確保、中心静脈穿刺などの手技を学んでいただきます。研修期間中にすべての麻酔手技をマスターするのは難しいですが、限られた研修期間の中で多くの手技を習得して欲しいと思います。
消化器外科では、下部食道から肛門までの上・下消化管における手術と肝・胆・膵の手術を行っています。鏡視下手術の割合は年々増えています。研修医には積極的に手術に参加してもらい、症例によっては指導医のもと助手だけではなく執刀医にもなってもらいます。
◆整形外科◆
整形外科では、骨折をはじめとした外傷、関節疾患、腰椎疾患などを中心に専門的な治療を行ってもらいます。研修医には、できるだけ多くの手術や手技に参加してもらいます。
ローテーション例
| 1年目 | 2年目 | |
| 4月 | 院内研修 内科 24週 (消化器・呼吸器・循環器) ※最初の2週間はオリエンテーション |
院内研修 内科 8週 (一般外来研修も含む) |
| 5月 | ||
| 6月 | 院外研修 小児科 4週 | |
| 7月 | 院外研修 産婦人科 4週 | |
| 8月 | 院外研修 精神科 4週 | |
| 9月 | 院内研修 救急科 8週 | 院外研修 地域医療 8週 (在宅医療含む) |
| 10月 | ||
| 11月 | 院内研修 麻酔科 4週 | 院内研修 院外研修 選択研修 24週 |
| 12月 | 院内研修 外科 8週 | |
| 1月 | ||
| 2月 | 院内研修 整形外科 4週 | |
| 3月 | 院内研修 皮膚科 4週 |
必修科研修を終えた残りの期間、研修医の希望により選択科を調整します。
3年目以降の進路を考慮した柔軟性のあるプログラムで、院内だけでなく協力病院での研修も可能です。
その他
受け持ち患者さん
・入職当初は指導医に付き、業務を覚える
・研修の修得状況を確認し、少人数の患者さんの副主治医として担当指導医に相談しながら入院患者さんのマネージメントを学ぶ
・研修医の力量にあわせ、徐々に患者さん数を増やし、上級医の指導下に受け持つ
当直
・月に4~5回の当直。
・基本的に病棟ではなく、時間外救急外来を担当します
症例の経験
・内科研修の間に入院症例(コモンディジーズから専門的症例まで)を経験できます。
・高齢者や複数の疾患を有する症例が多く、1人の患者さんから多くのことを学ぶことができます。
・救急症例を研修医が上級医と一緒に初療対応することができます。
※症例数は年度によって変動あり
経験できる手技
・研修医が少ないので、手技を経験する機会が多いです。
ある研修医が1年間で経験した手技の一例
静脈採血・動脈穿刺 数え切れず
中心静脈穿刺 32回
腰椎穿刺 9回
胸腔穿刺 10回
腹腔穿刺 8回
気管挿管 26回
※年度により変動あり